「蟹工船」ブームでたくさんの報道がされたが、もっとも感心したのは産経新聞だった。
新潮文庫がどうして急に売れ出したのか不思議がる書店や新潮社、あたかもブーム越しをしたかのような上野駅構内書店の話、コンビニ販売が火付けのような後発の出版社談話。しかし、産経新聞は、ネットカフェと漫画喫茶に張り付き取材して、そこにブームの原因があったと書いた。
去ること5年前に遡る。ようよう完成した当社のマンガ『蟹工船』を前にして、佐野白樺文学館長から一つの提案があった。
「若者に利用されている漫画喫茶やネットカフェなどに本を寄贈したい」と。佐野氏は大手インターネット会社の会長でもある。関東地方のチェーン店に交渉し、約1000冊のマンガ本が贈られる。
時は、共産党の志位氏が派遣労働者、パート労働者がネットカフェで生活している実態を国会でも告発し始めていた。今日、世界的経済悪化で非正規社員の解雇が社会問題になっているずーっと前である。
この寄贈先で読んだ若者の口コミと、志位氏の追求が時をほぼ同じく進行していったのは事実だ。当社が初めて直接販売したのは5年前の「赤旗まつり」、その催しだけで1000冊近いヒットとなった。
では、そもそも小林多喜二という大正時代の「古典」作品が、「流行語大賞」になるほどの再ブームをなぜ起こしえたのか。
それまでも新潮文庫や岩波文庫、新日本出版社で『蟹工船』は継続して刊行されていた。当社もここ10年近く、多喜二関連の研究書、入門書などを何冊も出してきた。しかし、せいぜい二刷が最高部数で苦戦していた。
「もっと若い人に多喜二の作品を広めたい」が口ぐせだった先の佐野館長は、多喜二の後輩、小樽商大出身である。
「わたしは、思い切ってマンガや映画など視覚に訴えるほうが効果的だと思う」と、同氏に提案したのはすでに四年近く前だ。
なぜ「思い切って」と言わざるをえなかったか。それまでの小林多喜二をはじめ、プロレタリア文学の作品は、ほとんど「聖域」のように劇画やイラストを取り入れていない。当時のままの文語体というのもある。
当社はすでに、アメリカ産の農薬米輸入反対のマンガ『米がなくなる日』や、現代医学で完治しないと言われる病気の挑戦マンガ『アトピー少食完治法』を刊行し、何刷りも重ねている。この経験を『蟹工船』に実現させたのだった。
 東銀座出版社の
やさしい文章教室
東銀座出版社の
やさしい文章教室
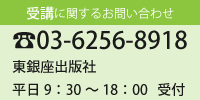


コメントをお書きください