ここに紹介するのは、小社から出版した『墨東惜春譜』(小池守之著)の作者が自著を書く過程で取材した経験談。そして、アララギ派という日本有数の短歌結社の草創期、無名の青年たちがいかに文学に熱心だったかの足跡である。
『墨東惜春譜』を出版して 小池守之
「ならしの文学ニュース」第四〇五号で、私がまとめていた記録の最初の部分が紹介されたことがあるが、今回、それを『墨東惜春譜―行路詩社ノート』(東銀座出版社)という本として出版した。
この本は、東京・墨田区の本所の地を拠点とした、職工や職人、大学生など一〇人前後からなる、アララギ派の短歌結社・行路詩社の青春群像を記録したものである。
時代は今から一〇〇年ほど前になる大正時代初期であり、私はこの記録をまとめるにあたって、行路詩社の青年たちの生活と作品の背景となった世の中の動向や本所の地の有様をできるだけ生なかたちで把握することに努め、そのために当時の新聞を大いに利用した。
『東京朝日新聞』を見ることが多かったが、これは明治時代から現在までの縮刷版が刊行されていて、図書館で容易に閲覧できることができたからである。
今回の場合『東京朝日新聞』は、自宅にも近い千葉市中央図書館で、明治四五年・大正元年から大正八年までのすべてに目を通した。目を通したと言っても、この当時の同紙は八頁が普通であり、それも見出しを見ていってこれはと思う記事をメモし、必要なものはコピーするという方法だった。そして、この新聞では不明な場合、国会図書館でマイクロフィルムになっている他の新聞にあたってみた。
これら新聞で調べた事実は、行路詩社の青年たちの行動の時期や内容を特定したり、本所の地のかつての有様を再現したりするのに、大いに役立つことになった。一編の記録を組み立てるうえで、それぞれが少しずつ骨格の役割を果たしたのだ。
ここでは、それらのうちから幾つかの例を紹介してみたい。
法恩寺の太田道灌木像
JR錦糸町駅から北へ六〇〇メートルほど行った所にある法恩寺は、江戸城を築いた太田道灌ゆかりの寺院として知られている。大正三年四月四日付『東京朝日新聞』に「太田道灌の渡初め 本所法恩寺橋の落成式」という見出しの記事が掲載されていた。法恩寺の近くにある法恩寺橋がこの時架け換えられたのだ。
落成式には東京市長や本所区長のほか多数の地元住民が参加し、法恩寺からは太田道灌の木像が運び出されたりしたという。記事に見えるこの時の賑わいの様子からは、当時の本所の地では川や橋が人々の生活といかに深く結びついていたかを知ることができる。
法恩寺に問い合わせたところ、明治二八年の寺院調書に宝物の一つとして「太田道灌之像」が記されているものの、これも含めて寺の什物は大正一二年の大震災ですべ て焼失したために詳細はまったく不明とのこと。この新聞記事を見た報恩寺の住職は驚いた様子だった。
新富座での観劇
行路詩社の、松倉米吉、早川幾忠、高田浪吉の三人が揃って、築地の新富座まで行き観劇したことがあった。これは高田浪吉の後年の回想録に出ているもので、武者小路実篤原作の「その妹」を見たという以外、時期などは明記されていない。
劇場と演目を手掛かりに調べていくと、大正四年一二月一〇日付『時事新報』の記事から、それは一一月二九日から一四日間にわたって上演されていた「二つの心」であることが分かった。高田浪吉は演目を間違って記憶していたのだ。
この頃の松倉米吉(一九歳)はめっき鍍金工場の職工、早川幾忠(一八歳)は無
職、高田浪吉(一七歳)は下駄漆塗りの職人であった。こうした彼らが連れ立って行動していた時を特定することができた一例である。
松倉米吉の雑記帳
松倉米吉の「雑記帳より」と題した文章には執筆時期が明記されていないが、この中に「東京としてはまれな大雪である」という記述があり、これは、東京では大正八年二月八日昼から九日朝にかけて三六年ぶりの大雪に見舞われたとある新聞記事から、大正八年二月に執筆されたことが分かった。
この五つに区分された文章には、行路詩代の他の四人のことも出てくるので、この頃の彼らの動向を知るうえで有り難い記事であった。
浜町産婦人科病院
松倉米吉の肺結核を大正八年に診察したというアララギ派歌人の医師・山本信一の勤務先について、『歌人松倉米吉』(筑摩書房・昭和五年)の著者である米田利昭は、これを「日本橋の浜・田病院」として調査したが結局不明だったとしている。
これについては、大正八年一一月二八日付『東京朝日新聞』の広告欄に「浜町産婦人科病院(日本橋区浜町三の七)」が出ており、ここに病院長以下六人の医師が列記してあって、その最後に「医学士 山本信一」と記されている。すなわち、大正八年九月一一日の朝に大量喀血した松倉米吉がその日、師の古泉ち千かし樫の強い勧めに従って受診のため出向いて行ったのは、この浜町産婦人科病院だったのだ。
松倉米吉の病状はこの後、坂を転げ落ちるように悪化していき、彼は結局二か月半後の一一月二五日に二三歳一一か月の短い生涯を閉じている。
上のような調査は、その結果を一冊の本の中に取り込むことで一区切りついたわけであるが、今にして思えば、ある期待を持って新聞を調べていた時の緊張感は格別であった。期待していたとおりの記事が見つかった時には、そうしたことは稀なだけに、何とも言えない充実感に包まれたものである。奥深い山中で稀少鉱物を探索しているような面白さがあった。
 東銀座出版社の
やさしい文章教室
東銀座出版社の
やさしい文章教室
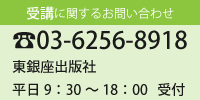


コメントをお書きください