今日の不況を鑑みると、時代はちがっても貧富の差は少しも変わっていないように思います。ましてや、東日本大震災と東電原発事故による関連倒産などを知ると、生活苦にあえぐ人はますます増えているようです。
ふと思って、自分が所属している文学同人に投稿した一文を転載します。
1、『貧しき人々の群』あらすじ
序にかへて。「小さき泉」の文から汲んだ、強く生きなければならない決意のような、人生はどんなに苦しくても前へ進まなければならないという姿勢を教師に問う形式で書かれている。1917年という日付がある。本文を読み終わったのちに「序にかえて」を再読したい。
一軒の農家、3人の幼い兄弟が鍋の薯を煮ている。貧しい光景が、土間の様子や子どもたちの空腹姿で想像させてくれる。突然、飛び込んできた野良犬も骨と皮である。薯の分配をめぐって兄弟が喧嘩して立ち回る描写や、室内にいる鶏たちの位置なども詳細に書かれている。そこは小作人の甚助の家で、親たちは働いていて留守らしい。
主人公の私(百合子自身と思われる)は、この甚助の家を木陰から見ていた。この貧しい農家に興味をもち、通りかかったおばあさんに同行してもらうが、子どもたちは敵愾心の目で見つめ、帰りがけには投石までしてくるのだった。私(主人公)はどうして彼らに嫌われたのかわからない。同情して親切心をかけようと思っているのに理解されなく、悲しむ主人公がいる。
ここ福島県の主人公の家は、祖父の代から開拓して財をなした地主だった。広い田畑をもち、小作人に貸して裕福な生活を送っているが、主人公は東京暮らしで夏休みに帰郷している。村民からは「東京のお嬢様」と呼ばれている。
「私は祖父の時代からたくさんの貧しい者に対して、どうしても何かしなければならない。今日まで、すべきことは沢山あったのに、臆病な自分が見ない振りをして来たのだといふやうな気のすまなさが、農民に対する自分の心を、非常に謙譲なものにしたのである」と省みる。
甚助の家を訪ねた翌日、甚助の母親が子どもを連れて謝罪に来た。しかし、いくら母親が叱っても子どもは謝らない。貧富の差を子どもは知っていて恨んでいるようだ。
村にはさらに貧しい善馬鹿と呼ばれる一家がいる。健全だったときに生まれた子も白痴で、母親は家出しておらず、祖母は家々の洗濯などを手伝って食を得ている。村の子どもたちからもからかわれている一家、私・主人公はかわいそうで面倒を時どきみている。村の子どもたちが善馬鹿一家をさげすむ光景は、親の貧しさからきていると主人公はみている。
貧しさは盗みも生んだ。私の畑の南瓜を盗んで見つかったのは、施しを与えていた甚助だった。彼は見つかっても反省していない。たかだか南瓜と思う私は、祖母の反対を押してきって甚助を許してしまう。食べられないから盗む者と、それを許してしまう自分に葛藤しながら。
こうした村にあることが起こる。町の豊かな夫人たちが集まる教会は社交化しているが、自尊心ばかり高い女たち。牧師の墓がある私たちの村に、故人の牧師ができなかった貧民救済募金を施してくれるらしい。名誉職がほしい夫人たちが滑稽に描かれている。催しの会長になった病院夫人を「大変肥つて背の低い人である。化粧に使ふ鏡は丁度胸ぐらいまでしか映らないものだつたので、常から上と下とはまるで別人のやうな恰好をしている人である」と揶揄している。
村人のなかで唯一、救われる人物として描かれているのが新さんだ。北海道に出稼ぎに行っていたが、父親も死に一人暮らしの母をみている。その母親は彼をいつも困らせらている。新さんは子どもたちにからかわれる善馬鹿をも愛おしく思っている。その新さんさえ、貧困と病気を苦に首つり自殺してしまう現実に、私・主人公は彼を救えなかったと苦悩する。
自分のささやかな慈善が本当の幸せを実現できないと主人公は悩みながら、「けれども、どうぞ憎まないでおくれ。私はきつと今に何か捕へる。どんな小さいものでもお互ひに喜ぶことの出来るものを見つける。どうぞそれまで待つておくれ。達者で働いておくれ! 私の悲しい親友よ!」と結ぶ。
2、小説に描かれた本質
主人公の私は百合子自身と思われる。17歳で書かれた小説は当時の文壇大家、坪内逍遥らに絶賛され、「中央公論」に掲載された。彼女のデビュー作。
東京で育った主人公は、祖父母のいる福島県の開拓村に夏休みを利用して帰郷していた。祖父は地主で小作人を雇い、農地を手広く貸す豊かさである。この豊かな若い少女が、自分たちの生活のために苦しむ小作人や村人に同情しつつ、社会の矛盾に目を向けていく。こうした小説の設定は百合子の育った環境そのものである。
ところどころに豊かに育ったゆえの目線が感じられるが、貧富の矛盾を感覚的にとらえて解決したいという、当時としては稀有な人生観、社会性をもっていた。同情や情けが、けして社会の矛盾を解決できないことにぶつかりながら、ささやかな物を貧しい村民に与えることで解決したい、何とかしたい作者の葛藤が何度も書かれる。当時の百合子の本音ではないか。
たとえば、甚助家の子どもや親をとおして一般的な貧しい農民・小作人を描きながら、農民の浅はかさ、教養のなさも素直に表現している。さらに善馬鹿一家のような村でも特に極貧の実態を書き、底辺に生きる人びと(小作人など)がさらに底辺の人間をさげすむといった、率直な感性で書いている。ここに若き百合子の素顔が見える。
このことは次のような描写にもみてとれる。
「ただ雌といふだけのやうになつた女房共」
「かうなると貧民共の獣性はすっかり露骨になつてしまつて」
けして配慮とか、表現の校閲を重ねたとは思えない、作者が感じたままの、ある意味では生き生きしたとらえ方でもある。当時の評論では「天才少女」として迎えられたが、各所にみられる行き過ぎた表現力は若さゆえの筆運びではないか。
しかし、大正初期の日本社会で17歳の若者が、自分の境遇に安堵することなく社会の矛盾、貧しさと豊かさの現実に向かい合っている小説は、実体験とはいえ、やはり稀有だっただろう。そうした視点、思考はやがて成長する彼女・百合子の萌芽期としてみることができ、その後の作品にふれることでプロレタリア文学の域を超えた、文学の力を読者に提供しつづけた。
3、宮本百合子の人間像
1899年(明治32年)、東京都文京区生まれ。父は建築家で中条精一郎、北大の建築やイギリス、アメリカなどで仕事するエリートだったが、祖父はあさか疎水という大規模な灌漑事業で知られた資産農家で、この体験から『貧しき人々の群』が書かれたといわれる。
育ちの良さはあったものの、それを超えた才媛と機知で日本女子大英文科に入学するも1年で中退、中央公論や東京日日新聞などに小説を発表、久米正雄、芥川龍之介らと通じる。すでに20歳で北海道のアイヌ民族の悲哀を取材し、「風に乗って来るコロボックル」は苦悩する民族を描いている。やがてアメリカに渡り、21歳で荒木茂と結婚するも5年余で離婚。この間、山川菊栄、与謝野晶子、野上弥生子らを知り、ロシアの飢饉に対し救援活動にとりくんでいる。
百合子の性格は、富裕層に育ちながらも弱者や困難な人びとにいつも目を向ける心情で、長編小説『伸子』などを残していた。29歳(1927年)のとき、ソビエトに湯浅芳子と旅しヨーロッパ各地を訪問、若いときから親しんだロシア文学の巨匠・ゴーリキなどに影響される。3年後に帰国、このときに日本プロレタリア作家同盟に加入、翌年に宮本顕治を知り共産党に入党している。34歳で顕治と結婚、この年に早くも駒込署に検挙され、この後も42年、昏睡状態で一時釈放まで検挙がつづいた。
顕治は治安維持法違反(戦後、この罪はないものとなる)で無期懲役、網走刑務所に送還、百合子は困難な時代でも『12年の手紙』や『播州平野』『乳房』『風知草』『歌声よ、おこれ』など歴史に残る作品を書きつづけた。
1951年、53歳の若さで死去、プロレタリア運動の星といわれただけでなく、日本文壇にも大きな影響と足跡を残し「多喜二・百合子賞」が設けられている。当時の「中央公論」「世界」「婦人の友」や大手新聞などにも執筆、依頼があり、プロレタリア作家が広く社会に認められた歴史があった。
個人的な百合子像を感想として述べる。
富農家に生まれながら、若くして社会の矛盾や貧富の差への怒りを百合子はなぜもちえたのか。もちろん個性ともいえるが、幼くして絵本やオルガンや小説に親しむ環境は豊かな感性を育てたのではないか。今でいう教育の成果である。この経歴は、戦後の一時期、共産党指導部の混乱により「ブルジョワ作家」と卑下される皮肉にも会う。
また、戦前の女性作家などの接点から社会への好奇と関心は高まっていたが、ソビエトを旅行したこと、プロレタリア文化運動に加入し、宮本顕治と結婚したことは大きな影響を与えられたと思う。また一方で、今日ではその先見性が評価される「ジイドとそのソヴェト旅行記」(1937年)を『ソビエト旅行記』(1936年刊)で批判、ソビエトの混乱を擁護している。当時の進歩的文化人、知識人がジイドを批判したのだったが、歴史をふりかえると、やがてジイドの予見したようにソビエトは崩壊した。これは誰も避けられない歴史的制約からきているのだろう。
プロレタリア文化・文学運動が広く社会に認められた作家としての実力、富裕な環境に育ちながらも安堵することなく社会の矛盾に目を向けていたこと、何より筆で主張をしつづけながら、かずかずの行動でも立ち向かった宮本百合子。大震災、原発をはじめとした今日の日本をみるとき、彼女から学ばなければならないものは多い。
(「ならしの文学」ニュースより)
 東銀座出版社の
やさしい文章教室
東銀座出版社の
やさしい文章教室
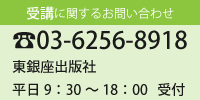


コメントをお書きください
伊藤ミチ子 (月曜日, 09 5月 2016 06:32)
民主文学の講演会で、百合子の話を聞きました。
宮本百合子の小説は、貧しき人々の群れ、伸子、12年の手紙だけで、違和感があり、あまり好きではありませんでした。百合子の生まれた境遇と自分との隔たりが余りにも大きくて、感情移入出来ませんでした。
ですから、その後の百合子は読んでいませんでした。
講演会での不破さんのあ話を聞いて、納得でした。