「明日の日曜日、うちに遊びに来ないか?」
彼はいつもより沈んだ声でわたしを誘ってくれた。この誘いが彼と永遠の別れになるとは知る由もなかった。
わたしは小学3年から隣り町・平井の柔道場に通っていて、そこそこ強かった。習い始めて半年後の江戸川区大会では10人抜きを達成し優勝した。
1年上の彼とも互角に練習していたが、どうしてか、わたしをかわいがってくれ、よく自宅に呼んでくれた。家業は駅近くでパチンコ屋や映画館を経営しているらしい。だから貧しかったわたしは、珍しいおやつに魅かれて何度も訪ねていたのだった。
「これで君と会えるのは最後かもしれない。家族で国に帰るんだ」
彼が何を言っているのかわからない。
「国に帰るって、ここじゃないの?」
「僕の国は北朝鮮なんだよ」
小学生5年のわたしにはまだ意味がわからなかった。
間もなく彼は道場に来なくなった。何度も遊んだパチンコ屋に行ってみたが、店は閉まっていた。彼が在日朝鮮人で祖国に帰還したのを理解したのは、ずいぶん時間がたってからだった。
「強い君なら大切にしてくれるだろうから僕の柔道着をあげるね」
それが彼との別れになってしまった。
昨年、ちば文倶楽部の公開講座「在日作家、朴重金鎬(パクチュンホ)氏を迎えて」が開かれた。
小さいが満席になって、ひと安心したのは運営委員だった。マスコミ、ミニコミ、文芸団体はもとより在日関係の朝鮮総連系、民団系の県下支部にも案内状を送っていた。
1935年、室蘭生まれの作家は両親が育った巨文島という小さな島の話から始まった。英国や日本が上陸し島を占領した歴史だったが、父親が日本に出稼ぎに来て在日になったことを語った。
「在日の人を強制連行したと言いますが、全員がそうではありません。自分の意志で来日した人もいたのです」
わたしは、強制連行された房総半島の海女さんや北海道炭鉱労働者の体験話を聞いたことがある。その過酷な話はとうてい作りものとは思えない過酷さだった。
約1時間、「自作を語る」というテーマは、ほとんどが自らの体験や両親の仕事だった。どんな著名な作家もかなり自分の体験をベースに小説化している、という、いつも文章講座で強調しているわたしは、「フムフム」とほくそ笑んでいた。
『回帰』『澪木』『犬の鑑札』などには、どれも共通して在日朝鮮人の仕事や祖国との複雑な心境がリアルだ。柔道友人が北朝鮮に帰還したのちの生活は知る由もなかったものの、朴作品によって帰還した困難さがわかる。
一連の作品はまた、港湾や焼き肉店などの労働現場が鋭く描かれている。船を操船するわたしだが、それでも知らない部品や機械の名称と操縦は多かった。北海道の船舶現場といえば誰でも小林多喜二の『蟹工船』を連想できるが、朴作品のそれもけして劣らない。時化にあう船内の描写はまるで読みながら船酔いしていくようだった。
もう一つ、どの作品にも驚かされたのは夫婦の性生活だ。けして三文小説的でない肉体と心理描写の葛藤は、ちば文倶楽部では手が出ない領域なので憧れてしまう。まして、作者は男性なのに女主人公に体現させて描く力は息を飲みながら読んだ。
芥川賞や直木賞は大手出版社の持ち回り賞として業界人は知っているが、一連の朴作品はそれを越える力量だと思う。本物の作家たちー松本清張のような緻密に構成し、島崎藤村のような社会背景の中に展開させる物語性、辻井喬(堤清二)のような大胆に発言する人は、なかなか今日の日本に見えない。朴作品には彼らと同じ匂いがするのだった。
わたしが指導する文章教室でほぼ強制的に朴作品を読書してもらった。日頃の教育がいいせいか、的確な感想がいくつも寄せられた。たしかに娯楽小説ではないし、ましてや圧倒的に多いと言われる私小説とも違うので楽しさは少ない。
しかし、自身の体験をべースにしているとはいえ、作家の裏に築かれた認識には次のような社会背景があることを知った。
かつて在日していた人は約60万人、それがいま、民団系45万人、朝鮮総連系3万人、日本に帰化した人が33万人と朴さんは語った。
「今後、在日、とくに朝鮮総連系の人たちの将来は見えてこない。ルーツを大切にし、伝統を失なわず、日本社会に役立つことをめざしてほしい」が講演結びの言葉だった。
在特会というヘイトスピーチをつづける差別団体が、堂堂と街宣できるこの国の非民主主義はいまさらだが、日本、韓国、北朝鮮三国がもっと友好になるには―。
わたしは柔道着をくれた友人を思い出しながら「日朝協会(日本コリア協会)」という友好団体にはいって、これから機関紙編集に協力する準備をしている。
 東銀座出版社の
やさしい文章教室
東銀座出版社の
やさしい文章教室
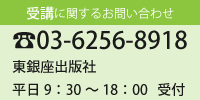


コメントをお書きください